工場のDX・IoT化で現場作業者の負担が増えていないか?
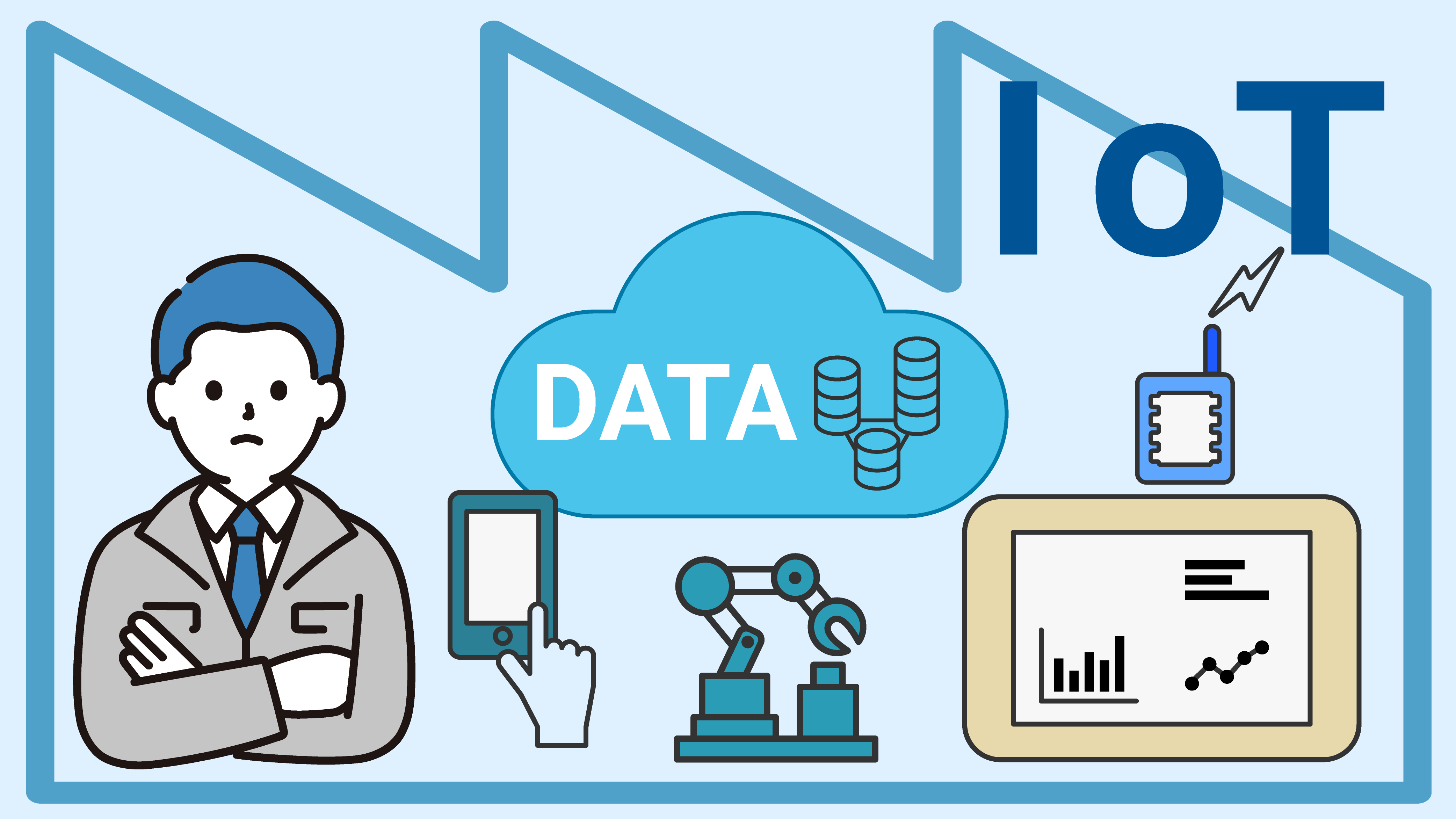
近年、多くの工場でDX(デジタルトランスフォーメーション)やIoT(モノのインターネット)が推進され、データの活用による生産性向上が期待されています。しかし、その一方で、現場作業者の業務負担が増加してしまっているケースが少なくありません。本来、DXの目的は業務を効率化し、生産性を向上させることですが、現場の実態を無視したデジタル化は逆効果になる可能性があります。本コラムでは、工場のDX化における現場作業者の負担増加問題について考えます。
1. タブレット導入が現場作業者の負担になっていないか?
デジタル化の一環として、工場の現場にタブレットが導入されるケースが増えています。しかし、作業者にとってタブレットの操作は必ずしも歓迎されるものではありません。
操作の手間
油まみれの手でタブレットを操作するより、従来のようにペンと紙で記録するほうが簡単で速い。
作業の中断
タブレットで作業開始・終了ボタンを押すだけならまだしも、作業内容や機械停止の理由を入力する作業が追加されると、現場の負担が大きくなる。
管理側の都合が先行
デジタル化により、できるだけ多くのデータを収集したいという管理側の意向が、結果として作業者の間接業務を増やしてしまっている。
現場の利便性を無視したデジタル化は、効率化どころか作業者の負担を増やし、生産性を低下させる要因になりかねません。
2. 量産工場におけるバーコード管理の落とし穴
量産工場では、個々の製品をバーコードで管理するケースが増えています。各工程の記録を取るために、作業者が工程ごとにバーコードをスキャンする仕組みが導入されることがあります。
管理側の視点では、
- 「紙よりバーコードの方が圧倒的に楽だろう」 という考えから、バーコードスキャンの導入が当然視されています。
しかし、現場作業者にとっては、
- これまで不要だった 「バーコードの読み取り作業」 が発生し、負担が増えます。
- 仮に1分半(90秒)の工程があれば、作業開始時と終了時にバーコードを読み取る必要があり、平均45秒ごとにスキャン作業をしなければならないことになります。
- これが 1日に何百回も繰り返されることで、作業者にとっては膨大な間接業務となります。
このように、DX・IoTの推進が現場に新たな負担を生むこともあるため、慎重な検討が求められます。
3. DX推進の本来の目的とは?
工場のデジタルデータ収集は、生産効率を向上させるために行うものです。しかし、データを取得するために作業者の負担が増えるのでは、本末転倒です。
例えば、
- ICチップを活用した自動記録:バーコードをスキャンしなくても、製品(もしくは容器)にICチップを埋め込み、自動で工程データを取得する仕組みを構築する。
- 作業者の負担を最小化する工夫:データの収集方法自体を見直し、作業者が意識せずに記録が取れる仕組みを導入する。
DX・IoTの担当者の役割は、単にデジタル化を進めることではなく、作業者の負担を増やさずに、工場全体の生産性向上につながる仕組みを設計することです。
4. 「稼働監視キットPro」で作業者の負担をかけずにデータを収集
「稼働監視キットPro」 では、
- 機械の稼働データ
- 作業者の位置データ
を、作業者の追加負担なしに自動収集 することができます。
さらに、これらのデータを組み合わせることで、
- 作業者の動きを分析し、作業日報を自動作成
- 「いつ」「どの機械(もしくは他の場所)で」「何の作業をしていたか」 をシステムが推測して記録
することが可能になります。
このように、作業者の負担をかけずにデータを収集・分析することが、本来目指すべきDX・IoTの形です。
まとめ
DX・IoTの推進は、工場の生産性を向上させるためのものですが、現場の実態を無視すると、かえって作業者の負担が増え、業務の非効率化を招きます。
- タブレット操作の増加や バーコードスキャンの負担など、現場の作業をデジタル化することで生じる問題を考慮することが重要。
- ICチップや自動データ収集技術を活用するなど、作業者の手を煩わせない仕組みを設計することがDX・IoTの本質。
- 「稼働監視キットPro」なら、作業者の追加負担なしで機械稼働データと作業者の動きを記録し、生産管理の効率化を実現します。
DXやIoTを推進する際は、「現場作業者の視点に立って、本当に効率化につながるのか?」を常に意識することが重要です。
サービス詳細
➡ 稼働監視キットPro サービス詳細はこちら
